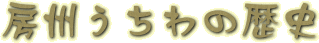 |
明治23年、那古の忍足信太郎が割き竹の加工を内職として手がけたのが房州でのうちわ作りの始まりとされ、それ以前は丸竹のままうちわの材料として問屋に出荷されていました。
明治30年になり、同じ町に住む岩城庄吉により本格的に「割き竹」の加工が始められ、大量の加工品を出荷するようになりました。その後、関東大震災(大正12年)で日本橋堀江町のうちわ問屋が壊滅状態になったのをきっかけに、問屋松根屋の当主 横山寅吉が船形に移り工場を建て、この地で完成品までの一貫作業を行うようになりました。
これにより「房州うちわ」が誕生しました。
|
|
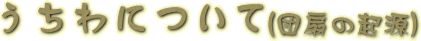 |
うちわの起源は古く、紀元前3世紀の中国(周の時代)からといわれておりますが、日本では正倉院や広隆寺の遺品として残り、万葉集にも歌われています。
うちわは風をおこして涼しくするために用いる物ですが、他に太陽の光りを防いだり、チリやホコリをさけたり、地方では祭りなどの儀礼的な事にも使われます。また、奈良・平安時代の貴族達の間では、顔をかくしたりする装飾品としても使われました。
うちわが一般的に普及するようになったのは、竹細工と紙の製法が広く行われるようになった江戸時代からだといわれています。有名な産地として、四国の丸亀、近畿地方の奈良・京都、関東地方の江戸があります。特に貞享年間(1684〜88)から元禄年間(1688〜1704)にかけて江戸の女性の間ではうちわを手にすることが流行しました。当時のうちわは扇面に浮世絵や役者絵が用いられ、網代で作った網代うちわ、絹を張った絹うちわなどの他に、柿しぶを塗った渋うちわは、台所で火を起こすのに使われ、庶民にも広く用いられる代表的な道具のひとつになりました。
また、その頃から盆や中元の祝儀用にうちわが使われるようになり、いつしか宣伝用うちわとして大いに活用されるようにもなりました。
|
|
 |
うちわの産地は現在日本では四国の丸亀、京都、そして千葉県の南端、房州の三芳・館山・富浦の3か所で、それぞれの製法に特徴があります。
丸亀のうちわは、平柄と呼ばれ、柄の部分が平らになっており、京都の差し柄うちわは文字通り柄の部分が木製で、骨が差し込んであります。
房州うちわは丸柄と呼ばれており、良質の女竹を用い、太さ1.5cm前後の竹を64等分して骨を作りそれを糸で編んで扇形に仕上げ、窓と呼ぱれる部分の両端から編んだ糸の房を垂れ下げてあり半円の格子模様の窓の美しさが特色です。
まんまるの型をしたもの、卵型、柄の長い丸型、大型があり、装飾品として愛用されるようになってから巾の広い楕円型のものや柄に根の部分を取り入れた個性的なものも見られる様になりました。
絵柄は、浮世絵や美人画が主流でしたが、最近では室内装飾品として民芸調のものも多く作られています。また、房州うちわは丸柄であることから、とても丈夫なのが特長です。
|
|
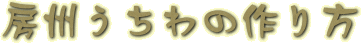 |
一枚の房州うちわが出来るには、まず材料の伐採から始まります。そして、その伐採された材料を24の工程で仕上げていきます。
はじめに竹の皮をむき、水洗いをして磨きあげ、次に竹を割り、柄の部分に穴をあけ、糸で骨を編み、柄を一定の寸法に切り、柄に柳の技を詰めます。さらにスゲを差し込み、編み終えた糸の両端をスゲに結び扇形に広げ骨組みが完了します。骨組が完了するとねじれをとるため目拾をし、穂刈をして骨の曲りを直すために炭火で焼き、紙を両面から貼り、余分な骨を裁ち落として、ふちどりの紙で周りをととのえ、ローラーできっちりとおさえて仕上げます。
|
原竹 → 皮むき → 磨き → 選別 → 割竹 → 選別 →
芽切り → もみ → 穴あけ → 編竹 → 柄詰 → 弓削 →
下窓 → 窓作り → 目拾い → 穂刈り → 焼き → 貼り →
面付け → 断裁 → へり付 → 下塗り → 上塗り → 仕上げ |
|
|
戻る

|